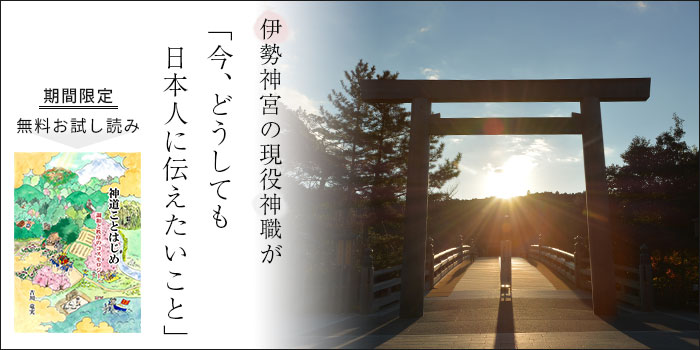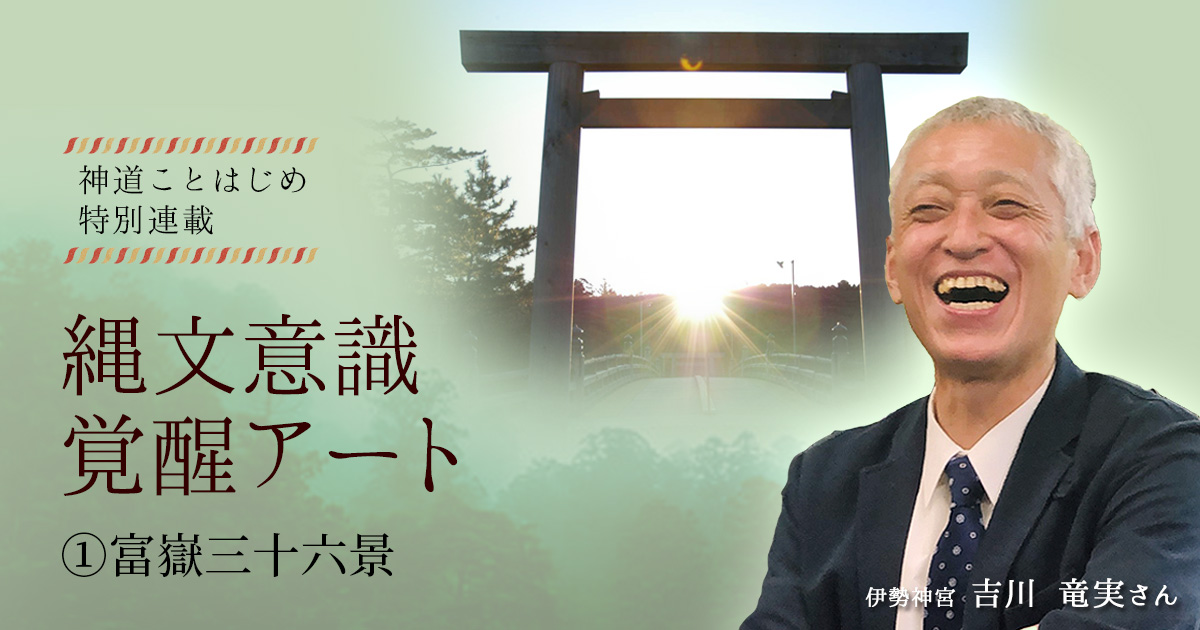連載再開にあたって ―はじめに―
吉川さん:今という時代は社会的にも環境的にも激動の大きな転換期を迎えているといわれます。そのような世の中にあっても、一人ひとりがその生命を充実させて楽しく心豊かに暮らすための感性(アイデンティティ)や智慧がすでに私たち自身の中に備わっていることを2冊のバンクシアブックスを通じてお伝えしてきました。
特に『神道の源流「縄文」からのメッセージ』では、1万年以上にわたって続いた縄文文化が過去の遺物ではなく、今なお一貫して日本人の精神性や志向性の奥底に宿っていることをさまざまな側面から焦点を当て論じました。
そしていよいよ本連載では、調和と共生の象徴でもある縄文的感性(縄文意識)を覚醒させる手がかりとして、アートを紐解いていきたいと思います。「縄文なのになぜ江戸期の富嶽三十六景?」と不思議に思われたことでしょう。
葛飾北斎は世界的にも突出した浮世絵師ですが、その根底に縄文的感性が見え隠れしているのです。そして縄文文化を終生こよなく愛し続けた岡本太郎がその生涯をかけて全身全霊で迫った芸術論と併せて、私たちの内にある縄文の意識を自覚する旅をご一緒に歩んでみたいと思います。
ひと魂で ゆくきさんじや 夏の原
【意訳】人魂になって夏の野原に気晴らしにでも出かけようか
右は浮世絵師の大家・葛飾北斎(1760〜1849)辞世の句ですが、臨終の際に彼は「天が私の命をあと5年保ってくれたら正真正銘の絵描きになることができただろうに」と語ったと伝えられています。終生絵を描くことに飽くなき探究心を抱き続け「画狂人」とも自称した北斎。
アメリカのフォトジャーナル誌『LIFE』が1998年に発表した「ザ・ライフ・ミレニアム」紙上で「この1000年で最も偉大な功績を残した世界の人物100人」の中に唯一日本人として北斎が選出されています。
ハイクオリティー溢れる作品の数々を3万点以上も生み出した稀代の天才絵師・北斎を代表する最高傑作といえば、誰もが日本美術史の教科書にも必ず出てくる『富嶽三十六景』(実際は46景)を挙げるのではないでしょうか。
その初版は1831年から1835年頃に出版されており、この時期は北斎の72〜76歳の晩年期にあたっていますから、当時の人々の平均寿命(32〜44歳)からすれば、齢とは無縁の彼の創作意欲の旺盛さには驚愕せずにはいられません。
ところで、北斎の『富嶽三十六景』の主題であった富士山を望むことができる絶景として、万葉歌人の山部赤人は大和から駿河の田子の浦に下り立ち、神代の昔からの威容を誇る富士山を神格化して次のような長歌と反歌を詠んでいます。
山部宿禰赤人が不盡山を望てよめる歌一首、また短歌
天地の 分かれし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる 富士の高嶺を 天の原 振り放け
見れば 渡る日の 影も隠ろひ 照る月の 光も見えず 白雲も い行きはばかり 時じくそ
雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎゆかむ 不盡の高嶺は
反歌
田子の浦ゆ打ち出て見れば真白にぞ不盡の高嶺に雪は降りける
(『万葉集』巻三より)
実はこの北斎の『富嶽三十六景』に、縄文意識の覚醒を促してくれるアートとしての可能性が秘められているのではないかと思わずにはいられないのです。
そのひとつのヒントが、尾形光琳の系統をひく日本画の「琳派」です。浮世絵から洋風画法までさまざまな画法を学び、多彩な画風を生み出した北斎が、「どの流派にも属さない」と独立する前に長く属していた流派で、北斎はその頭領の画号である「宗理」を用いて襲名することをも鮮明にしていたのです。
かの縄文土器の発見者であり縄文意識の体現者であった岡本太郎は、浮世絵と共にこの琳派を高く評価していましたが、なかでも大絶賛したのが光琳の描いた『燕子花図屏風』『紅白梅流水図屏風』だったことを挙げておきたいと思います。
拙著『神道の源流「縄文」からのメッセージ』の中で、縄文の人々のモノヅクリには、目には見えない「自然(産霊)の造化力(働き)」というエネルギーを表そうとした意図を感じざるを得ないとご紹介しました。
これを踏まえて縄文意識とは何かを端的に述べるならば、「瞬間的に時空間を飛び越え、無我や没我の境地となって真の自己を解き放ち、あるがままの姿で自由に生ききっていく意識」として、以降『富嶽三十六景』を詳しくみていくことにいたしましょう。

https://www.fujibi.or.jp/our-collection/profile-of-works.html?work_id=6150
吉川 竜実さんプロフィール
皇學館大学大学院博士前期課程修了後、平成元(1989)年、伊勢神宮に奉職。
2016年G7伊勢サミットにおいて各国首相の伊勢神宮内宮の御垣内特別参拝を誘導。通称“さくらばあちゃん”として活躍されていたが、現役神職として初めて実名で神道を書籍(『神道ことはじめ』)で伝える。
知っているようで知らないことが多い「神道」。『神道ことはじめ』は、そのイロハを、吉川竜実さんが、気さくで楽しく慈しみ深いお人柄そのままに、わかりやすく教えてくれます。読むだけで天とつながる軸が通るような、地に足をつけて生きる力と指針を与えてくれる慈愛に満ちた一冊。あらためて、神道が日本人の日常を形作っていることを実感させてくれるでしょう。
下記ページからメールアドレスをご登録いただくと、『神道ことはじめ』を第2章まで無料でお試し読みいただけます。また、吉川竜実さんや神道に関する様々な情報をお届けいたします。ぜひお気軽にご登録くださいませ♪