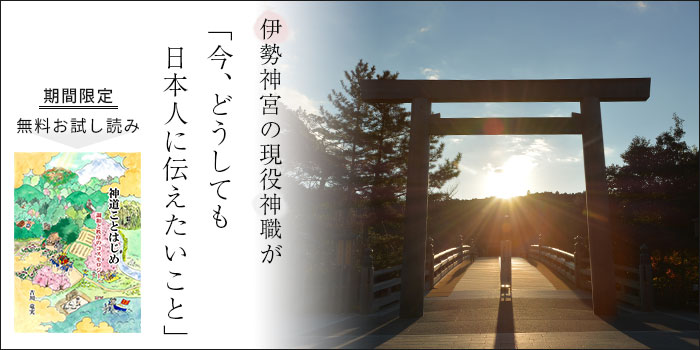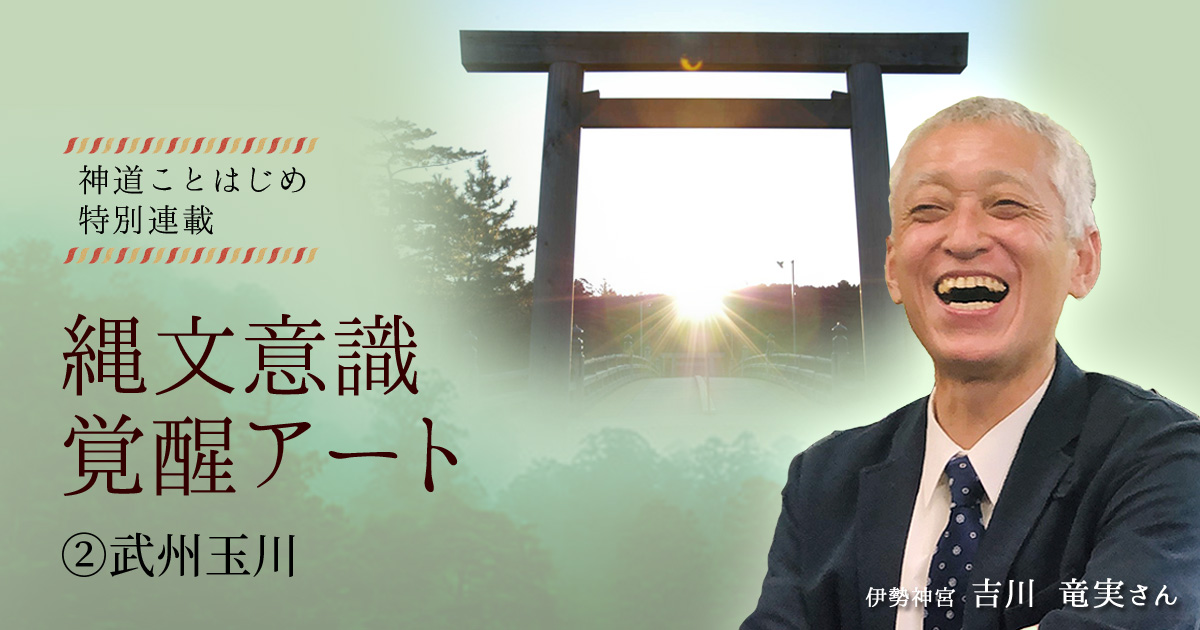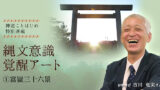先人たちが残してきたさまざまなアートには、調和と共生の象徴でもある縄文的感性を覚醒させる手がかりがあるようです。そこで世界的にも突出した浮世絵師・葛飾北斎の「富嶽三十六景」を題材に、日本人の精神性を縄文に遡って探究していた岡本太郎の芸術論を交えつつ、内なる「縄文的感性」の覚醒に向けて働きかけてまいりましょう。
吉川さん: 『富嶽三十六景』の中で最も簡略化された大胆な構図を有し、かつ凜とした静謐さ漂う、臨場感溢れる一枚の絵として圧倒的人気を誇るのが『武州玉川』ではないかと思われます。
当絵の描画地点は武蔵国府中(現東京都府中市)における玉川(=多摩川)河畔から富士の雄姿を眺望できる場所となっています。
『武州玉川』の構図は近景・中景・遠景の三つの要素から構成されています。
近景においては、先ず民家や船宿すらない物寂しい岸辺に荷を積んだ馬をひく農夫らしい男が一人佇む姿が描かれています。
そして玉川の流れを右上から左下に向かって斜めに配することによって急峻な流れを醸し出し、不定形な描線を重ね合せて川面に美しい波紋を出現させ、対岸より藍をぼかし摺りにすることによって清新な水質が感じられるように描き出されています。
その川面には霊峰・富士へ視線を送る船頭の操る一艘の舟が滑るように静かに向こう岸へ乗客を導いている様子が描写されています。
中景では「すやり霞」を帯状に配置し、遠景においては玉川河畔より実見できる大きさの富士よりも壮大にして威風堂々たる姿で霊峰を描き切っています。
そもそも「すやり霞」とは大和絵の伝統的な手法で場面を切りかえる際によく用いられますが、とりわけ北斎がこの手法を駆使して対象物を描く時には時間や空間を超越させる意味合いが強かったといわれており、実に近景と遠景との距離感がよく表現され、数多の庶民の憧れであった霊峰・富士がまるで異界にでも厳然と聳えるように表現されているといえるでしょう。
この絵を幾何学的な面から観察すると、霊峰の右側の稜線は水面の舟の右舷側面線とほぼ平行に引かれ、舟の舳先を頂点とするその側面線と岸辺に佇む一人の男のポイントを結ぶ線よりできる山形の屈折線は富士両翼の稜線とほぼ相似形の関係をなしています。
また近景にいる岸辺の馬の地面に向けて下げられた頭から背へと至り更に尻尾へ向かって伸びる小さな山形の図形は、遠景に存する大きな霊峰の稜線シルエットともフラクタルの関係になっていることが読み取れます。
このような相似形の関係を有するのは、北斎が各個別に存在する霊峰・舟・人馬を一枚の絵として一体の関係性にあることを暗示したかったからに他ならないと推測しています。
『富嶽三十六景』の出版には、当時の庶民の間で富士信仰が大いに隆昌を誇っていたことが契機となっています。
また室町時代の世阿弥の能で著名な謡曲『富士山』においては「然れば本号は不死山なりしを群の名に寄せて富士山とは申すなり。是蓬莱の仙境たり。」と見られ、霊峰・富士は秦の始皇帝が不老不死の仙薬を求めて徐福を派遣した伝説にまつわる仙境「蓬莱山」に比定される信仰のあったことも窺われます。
中国山東地方の東海中にあるというこの山には、仙人たちが白色の鳥獣と暮らす金玉の宮殿があり、玉の木々が密生する理想郷で、遠く望めば雲や霧のようであり近づけばどこかへ消え去ってしまう幻のごとき異界の存在であるため、常人にはなかなか辿り着けないところと伝えられてきました。
このような信仰を背景にして改めて『武州玉川』を凝視すると、北斎がこの絵で意図した狙いは江戸庶民の憧憬の的であった「富士山」を目のあたりにできる「蓬莱山」として顕現させて提示することにあったと思考されるのです。

https://www.fujibi.or.jp/our-collection/profile-of-works.html?work_id=6209
吉川 竜実さんプロフィール
皇學館大学大学院博士前期課程修了後、平成元(1989)年、伊勢神宮に奉職。
2016年G7伊勢サミットにおいて各国首相の伊勢神宮内宮の御垣内特別参拝を誘導。通称“さくらばあちゃん”として活躍されていたが、現役神職として初めて実名で神道を書籍(『神道ことはじめ』)で伝える。
知っているようで知らないことが多い「神道」。『神道ことはじめ』は、そのイロハを、吉川竜実さんが、気さくで楽しく慈しみ深いお人柄そのままに、わかりやすく教えてくれます。読むだけで天とつながる軸が通るような、地に足をつけて生きる力と指針を与えてくれる慈愛に満ちた一冊。あらためて、神道が日本人の日常を形作っていることを実感させてくれるでしょう。
下記ページからメールアドレスをご登録いただくと、『神道ことはじめ』を第2章まで無料でお試し読みいただけます。また、吉川竜実さんや神道に関する様々な情報をお届けいたします。ぜひお気軽にご登録くださいませ♪